【小論文出題パターン解説】テーマ型
問題文が短い「テーマ」のみで出題される小論文について解説。出題文がシンプルだからこそ事前の対策が大切です!
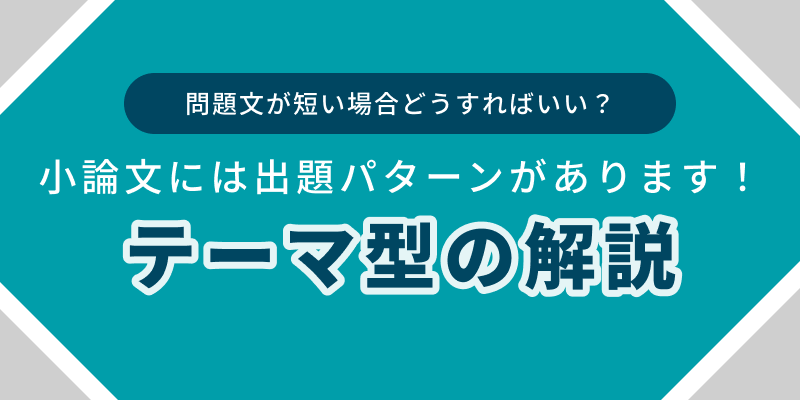
「入試対策で小論文の問題を解いてみたけど、どうやって解いたらいいかわからない…」
そんな悩みを持っている受験生も多いのではないでしょうか。
この記事は、大学受験の小論文で多くみられる問題の形式を解説する「小論文出題パターン解説」シリーズのテーマ型編です!
テーマ型の小論文について、概要・抑えるべきポイント・具体的な対策法について解説していくので最後までお見逃しなく!
テーマ型とは
テーマ型の小論文とは、簡単に言ってしまうと「問題文が短い」小論文です。
図やグラフ、文章といった出題内容がなく、「あるテーマ」についての解答者の見解が問われます。
多くの小論文試験で採用されている課題文型との大きな違いは、上記の3種類全てにおいて解答の自由度が高く受験者の知識量によって差が生まれやすいことです。
テーマ型の小論文試験は主に3種類に分類することができます。
種類ごとの具体的な構成については「具体的な対策法を解説!」で解説しています。
①賛否とその理由を問うもの
例:死刑制度に対する賛否とその根拠を論じなさい
②キーワードの説明を求めるもの
例:選択的夫婦別姓制度について説明しなさい
③話題だけが与えられるもの
例:新型コロナウィルスが学校教育に与えた影響について自由に論じなさい
解答作成で抑えるべきポイント
現状の説明・分析
テーマ型の小論文で最初に抑えるべきなのはテーマに関する現状の説明と分析です。
例えば①の例であれば死刑制度についての世界情勢や世論、主な争点について触れることは必須だと言えるでしょう。
テーマについての知識が不足しているとこの部分の内容が薄くなってしまいます。
賛否や意見の提案
上で紹介した①・③のパターンのテーマ型小論文では自分の立場をはっきりとさせて書くことが重要になります。
つまり①の場合、最初の段落で自分が死刑制度に賛成か反対のどちらの立場から意見を述べるのかを記述するべきです。
論理性
小論文試験全般に言えることですがテーマ型では論理性が非常に重要になります。
特に③のような受験生のアイデアに依存する設問だとオリジナリティを出そうとして論理性が甘い解答になる傾向があります。
小論文試験ではオリジナリティも重要ではありますが、最も重要なのは文章の論理性です。
どれだけ素晴らしいアイデアでも論理的に正しくないところがあれば大幅な減点になってしまうので細心の注意を払う必要があります。
高得点を取るためのコツ
では、テーマ型の小論文試験で高得点を取るためにはどのような対策をすれば良いのでしょうか?
受験学部の知識を積極的にインプットする
テーマ型の小論文では受験生の知識量によって文章のクオリティに大きな差が出ることが特徴です。
課題文型や講義理解力型などはそこで与えられた情報をもとに文章を作成するため、事前の知識があまり多くなかったとしても太刀打ちできますが、テーマ型では何も書けなくなってしまう恐れがあります。
そのため、日頃から受験学部に関連する内容の本を読んだり、ニュースを確認するなどして知識を蓄えていくことが非常に重要です。
箇条書きを作成する
他の形式の小論文でも言えることですが、テーマ型の小論文を解く時には文章を書き始める前に書こうと思っている内容について箇条書きにすることをおすすめします。
①の例であれば死刑制度のメリット・デメリットをそれらをサポートする根拠と共にまとめることや、③であれば自分のアイデアと関連するニュースやデータをまとめておくことで論理的に正しい文章構成を作りやすくなります。
さいごに
課題文型の小論文について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
ヒントとなる図や文章がなく、自分の知識のみで小論文を解かなければいけないので、最初は難しく感じるかもしれません。
しかし、練習を重ねていけば必ず素早く・的確に解答できるようになります。
ルークス志塾では、いつでも小論文のプロ講師があなたの受験相談に応じます!
小論文に行き詰ってしまった方、もっと上達したい方は、
ぜひルークス志塾の無料相談会にお申込みください。

- プロや経験者のサポートが得られる!
- 仲間とともに楽しく受験を乗り越えられる!
- 人のつながりで課外活動がやりやすくなる!
